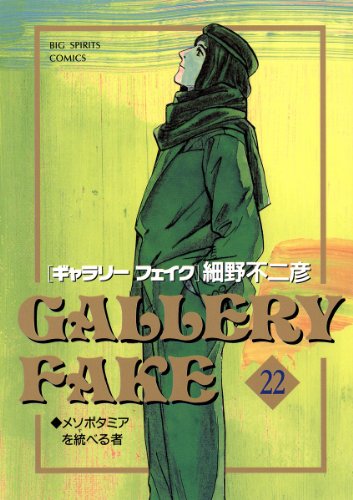https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20201111/2000037132.htmlwww3.nhk.or.jp
・・・・・・・京都大学で先月開かれた、縄で人を縛ることをテーマにしたシンポジウムで、着物姿の女性を縛るようすを実演し、動画をインターネットで配信していましたが、大学は内容に不快感を示す意見が寄せられたことから、公開を取りやめました。
先月24日に京都市左京区の京都大学で開かれたシンポジウムは、縄で人を縛る「緊縛」をアートとして紹介しようと京都大学文学研究科の教授が企画したもので、学生などおよそ80人が出席しました。
会場は文学部の講義室が使われ、この中で男性が実際に着物姿のモデルの女性を縛るなど、およそ30分にわたって実演が行われました。
シンポジウムの様子は、動画投稿サイト「YouTube」で配信され、海外で話題になるなどして、50万件以上のアクセスがありました。
一方で、この動画を見た人から「女性を軽視している」とか、「これは学問なのか」など不快感を・・・・・・・
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201111/k10012706891000.htmlwww3.nhk.or.jp
そこで、アートを描いた傑作マンガ「ギャラリーフェイク」で、ある事情のために非常に有名なエピソード…22巻収録の「カリスマ真贋」を連想。
何でこれが有名なのかというと、現代アートの村上隆氏をほうふつとさせるキャラクターが登場し、それを批判するという話の流れが、非常に話題を呼んだんですね。
作者の細野不二彦氏は、実は例の「スタジオぬえ」と非常に深いかかわりがあり、つまり作中で対比的に描かれている、オタクアートとしてメカや美少女をデザインする職人気質のデザイナーみたいな人を良く知っている立場だ。だから話が二重三重にも深い。
だが、そこはあまりに面白すぎるが、話がそれるのでスルーしておく。
で、そこのクライマックスが、
村上隆もどきアーティストを「ありていにいえばパクリ屋」と批判したフジタに 「それは古い発想。これはサンプリングであり…それはそもそも僕たちの共通体験で…それにリスペクトを……」と、アーティストはなにやらややこしい理論を掲げて反論する。
で、フジタがそれにどう”再反論”したかというと、突然、彼の財布をひったくって、中の札束をぶちまけるのだ。
そして、ドロボーと責める彼に、「これはマネーがあらゆる境界を突破する流動性を持つことをパフォーマンスで示した、俺流のアートなんだ!!」と皮肉をぶっぱなすのである。
これはもちろん、「そんな、俺がこの非常識な行為をでたらめでこじつけたテキトーな理屈と、お前のサンプリングだリスペクトだって議論は同じなんだよ!!」という逆説的な意味合いであります。

実際、「アート」も「思想」も「宗教」も、似ている部分があるのは、その優劣を決める価値基準は定めるわけにはいかないし、そもそも不可能である、ということだ。
釈迦キリストムハンマドソクラテスと、大川隆法文鮮明の間に、差をつけたいのはやまやまだろうが、さくら、それをやったらおしめえよ(寅さん風)。
宗教とは「言ったもん勝ち」なのである。
m-dojo.hatenadiary.com
たとえば今回、緊縛が女性だったかなんかで「女性を軽視している」といわれたそうですが、そうなのかどうか。そしてまた、アートであるなら差別ではない、かどうかもあやしくて、差別であることとアートであることは両立したりもするでしょう。
…美であると否とにかかわらず、差別は差別なのだし、差別であると否とにかかわらず、美は美なのである。二つは別の価値観によるものなのだ。とすれば、二つの価値観による組み合わせは次の四つになる。
1:美しくて差別でないもの
2:美しくなくて差別でないもの
3:美しくて差別であるもの
4:美しくなくて差別であるもの。このうち最悪の組み合わせである4は特に擁護する値打ちはなく、 批判されても誰も反論はしないから議論が起きない。最善の組み合わせである1も誰も批判や糾弾はしないから議論が起きない。2も消極同士の組み合わせであるから目立つことがなくやはり議論は起きない。結局いつも3の「美しくて差別であるもの」だけに議論が起きる。
m-dojo.hatenadiary.com
そのため124を含む四つの判断の組み合わせがあること、すなわち二つの価値観の並立こそが議論の本質だということが見えにくくなっているのだ…
ということで、
トリエンナーレとその周辺のもろもろを思い出してください。
「なごやトリエンナーレ」なんてのもあったね。
m-dojo.hatenadiary.com
「トリカエナハーレ」なんてのも
m-dojo.hatenadiary.com
一方で、海外のギャラリーでは。
ロンドンのサーチ・ギャラリーは女性の裸体の上にイスラム教の信仰告白の言葉をアラビア語で記したものをストライプ状に重ねた絵画についてイスラム教徒が「イスラム教に対する冒涜」と抗議したため絵画全体を布で覆って対応。表現の自由について議論する契機に、とのこと。https://t.co/45tS6LbHWO
— 飯山陽 Dr. Akari IIYAMA 新刊『中東問題再考』増刷決定 (@IiyamaAkari) 2019年5月8日
ネットで観れました。
— amamoriくん (@rainywoods2001) 2019年5月10日
全体的に星条旗を思わせる構図。
左上にユダヤの六芒星群。ストライプにイスラム教の聖句。透けてみえるのが、「グランド・オダリスク」というフランス人アングル作の有名作品でトルコ王室の後宮(ハーレム)の女性の裸を描いたもの。
ムスリムが不快に感じる要素満載でしょう。
「勝手に大文字焼き」も「勝手に『、』を打って『犬』にする」なども、前衛アートだと言い張ったら……
m-dojo.hatenadiary.com
んで、何がアートか、アートでないかを決めるのは、タイトルのような要件ではないでしょうか(笑)
ちなみに木村草太氏は、それは「専門家」が決めるのだ、とこれはこれで割り切りがすっきりした主張をしている。
「…芸術展の展示の適切さは、芸術の専門家により自律的に判断されるべきものだ。市長や官房長官は行政のプロであって、芸術判断の専門家ではない。市長や官房長官が、表現内容の適切さを理由に介入するのは、越権行為だろう。」(「沖縄タイムス+」より)
m-dojo.hatenadiary.com
しかし、こういうふうな「何がアートかってどう決めるの?」という話は、落語「はてなの茶碗」が見事な肩透かしを食らわせており、あまりに鮮やかなので「ギャラリーフェイク」にもこの話がモチーフとして登場したことがあったな(笑)
www.youtube.com