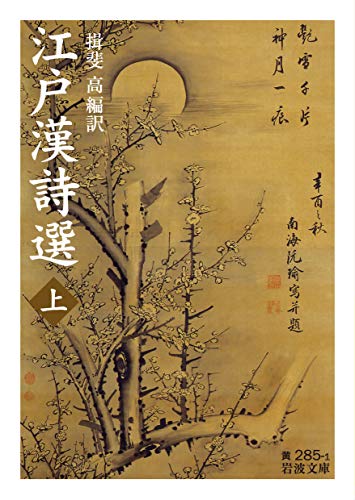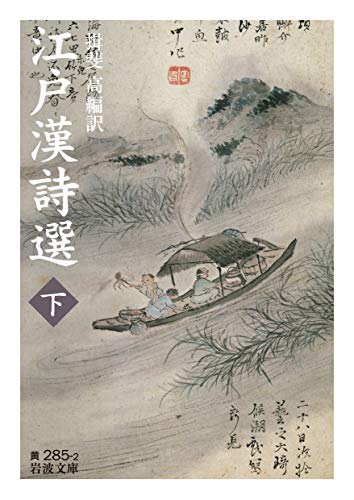「江戸漢詩選」(上)読んだ。
江戸時代に大きく花開いた日本の漢詩の世界。二百六十年余の間に活躍した詩人から百五十人・三百二十首を選び、およそ生年順に配列、詩人小伝や丁寧な語注と共に編む決定版アンソロジー。上巻は幕初の藤原惺窩に始まり江戸中期まで、林羅山、新井白石、祇園南海、荻生徂徠、伊藤仁斎、菅茶山らの詩を収録する。(全二冊)
それほど自分は詩心がなく、詩それ自体を味わうというより、何かの逸話や故事に絡んでないかとか、今の時事に関連付けるようなものはないか、との視点で読みがち
「ヤツら(俺ら)は詩を読んでいるんじゃない、情報を読んでるんだ!」
です。
それで、読んでみたら、こういうタイムリー?な一編がありました。
書懐(懐(おも)いを書(しょ)す)
若し吟詠もて 情志を述ぶること無くんば
今古 何に因って思ひは移す可けんや
誰か謂ふ 弄文は我が事に非ずと
二南 半は是れ 婦人の詩
解説によると、作者は女性…井上通女なわけです。
詩(うた)で心を 言えないならば
何で思いを 伝えるの
女の文学 要らぬと言うが
あのうた このうた 彼女たち
こういう時、説明抜きで古典から引用したり故事を書いたりして「そこは、ふふふ、お分かりでしょ?」と投げかけるのはむしろ漢詩のおしゃれなスタイル。
あんたバカァ?

そういう部分を説明すると、
「二南」とは『詩経』国風の召南と周南の詩のことだという。この半分が女性の作だ、と。(それが事実かは調べればわかるだろう。俺は調べん)
また、この漢詩には和歌も添えられていたそうです。
「ゆくすゑに ちまたの数は わかるとも わがふみそめし 道はまどわじ」
(自分のこれからは、いくつも分岐…転機や可能性があるでしょう。しかしどんなことがあっても、自分が選んだこの道=文学の志を、迷うことはない)
ちゃんとウィキペディアには項目が立っている。
ja.wikipedia.org
ここにこの詩を入れてみようかな。