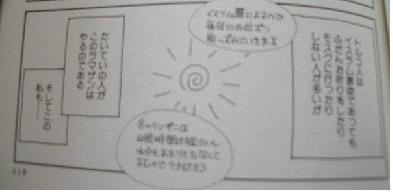昨日の朝日新聞に「トルコで私も考えた」の作者インタビューが掲載されていました。
その中で「今年2月に、連載をいったん終了する」という一文があったのでご報告する。
いやあ惜しい、惜しい。以前、こう書きましたね
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20070524#p2
最後にトルコの話に戻すけど、「イスタンブールに置かれた日本の目」こと
この作者は今でも連載しているのかな。
- 作者: 高橋由佳利
- 出版社/メーカー: 集英社
- 発売日: 1996/12/16
- メディア: コミック
- 購入: 21人 クリック: 182回
- この商品を含むブログ (48件) を見る
国際的な「漫画のノーベル賞」もよろしいが、日本の情報機関がエッセイ漫画家を組織的に養成、世界各国に送り込んでレポートを漫画で描かせる・・・というのはいかがでしょうか(笑)
でもマジ、こういう人が一人いるといないで大違い
これに付け加えるようなことは無い。実際、外務省の連中がワインだ国会議員の接待だに税金を使うなら、高橋由佳利への原稿料に機密費から上乗せして、連載を続行させてほしいよ。
いま、トルコは新興Bricsのあとを追う経済成長を見せているし、これも以前書いたようにイスラム政党が与党として支持を得た結果、蓋世の「啓蒙専制大統領」ケマル・パシャが築いた「近代としてのトルコ」が大きく変わる気配を見せている。
それは、イスラーム原理主義による近代からの揺り戻しと、ケマルがある意味無理を承知で作った近代が、さらに洗練された「第二次近代、新近代」になろうかという二つの運動の狭間・・・。
しかも、それが期せずして同じ方向を向いている・・・・という、実に思想史的に面白い時代なんである。

いやこの漫画はそういう大状況に関しては意識的に?距離を置いているようだが、賢者は門を出でずして天下を知る、てなもんである。
トルコの人はたいてい普段の礼拝をしないが、ラマダンには参加する」という一こまの情報が、どれだけ国際理解の助けになるか。住宅事情、電力事情、人気歌手・・・すべてが楽しく、驚きの教養となる。
連載終了は、まことに残念だ。しかたないので、これまでの残り部分の単行本化を待とう。
トルコについてじきに書きたい
実は例の「政治と宗教」「自由と不自由」「近代と非(「前」ではない)近代」があまりにも複雑に絡み合う「スカーフ問題」がトルコで今、また大きく変わろうとしているらしい。
これも含めてトルコ関連資料をいろいろと集めたのだが、まだ怠慢ゆえに書いていないのが現状だ。
近いうちに、一回ぐらいは書いておきたい。
呉智英にトルコを旅させたい。 俺も行きたいけど
このへんの宗教と、近代の逆説というのは呉智英が初期から書いていたもので、自分の論も口真似みたいなものだけれども、SAPIO編集部当たりで旅費を出して、先方の保守派・進歩派(この区別もそうやりゃいいんだか)知識人との対話の場もセッティングして彼に見聞させてみたいものだね。今以上の逆説を、社会のあちこちに見つけることができるだろう。
それとは別に自分も、いつかトルコに行ってみたいものだ。上のような問題を自分でも見てみたいというのはあるが、アタチュルクの霊廟に参拝したいし、戦跡であるダーダルネスも見てみたい。もちろんオスマン帝国の遺産もこの目で見たいし、トルコ料理の本場ものも食べてみたいし。