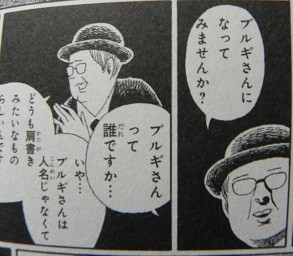上の記事で筒井康隆について触れたから、次に星新一・・・というわけではない。
さっきはてなアンテナ経由で
■『時間ループ物語論』
http://d.hatena.ne.jp/gaikichi/20121231#p5
- 作者: 浅羽通明
- 出版社/メーカー: 洋泉社
- 発売日: 2012/10/25
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 4人 クリック: 152回
- この商品を含むブログ (32件) を見る
を見た(ちなみに自分も何回かこの本を紹介しています)。
ところがそこの記述に
本年末は急に『週刊文春』で取材される側になってしまった浅羽先生
とあり、ん?なんだなんだ?こういうのはグーグルよりtwitter内の検索がいいな・・・→確認して数分爆笑(失笑)
のついでに、このちくまウェブでの連載を知ったというわけだ。
「開始」と書いたが、よく見ると隔週連載でもう4回目、11月にスタートしていたのだな。書籍の検索通知機能はあるが、ウェブ連載の告知機能はないものな。
■星新一の思想 −とうにユートピアを過ぎて
http://www.chikumashobo.co.jp/new_chikuma/asaba/01_1.html
(からリンクが伸びています)
第1、2回 秀頼世代のための序章─「城のなかの人」精読(上)(下)
第3、4回 「商品としての小説」と「革命的自営業者(ブルジョワジー)としての作家」(上)(下)
自分はこれを熱望していた。
過去の文章を再録すると
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20120626/p3
(略)・・・一部の星新一ショートショートは、突き詰めていくとマイケル・サンデルばりの正義論、法哲学論議になると前々から思っている。
浅羽氏の過去の著作にも、そういう議論のために星SSを引用していた箇所がたくさん有り、一度本格的にそういうのを、まとめて書いて欲しかったと思っていたのだ。このブログでもそういうことを何度か書いていたかな。
エア新書で作ると
こんな感じ。(タイトルがちょっと長いと「エア新書」は字がはみ出るので、センスなしの題名になってしまったが・・・)
どれぐらい連載が続くのかは分からないが、これは楽しみだ。
こんな講演映像もある。
「コミック星新一」第三弾では『ひとつの装置』が漫画化されている
星新一のショートショートを基にした漫画を大家、新鋭取り揃えて描き綴っていく「コミック星新一」、てっきり二冊で終了した・・・と思い込んでいたのだが

- 作者: 星新一
- 出版社/メーカー: 秋田書店
- 発売日: 2004/07/15
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 12回
- この商品を含むブログ (37件) を見る

- 作者: 星新一,志村貴子,小田ひで次
- 出版社/メーカー: 秋田書店
- 発売日: 2003/06/01
- メディア: コミック
- 購入: 3人 クリック: 35回
- この商品を含むブログ (47件) を見る

- 作者: 星新一
- 出版社/メーカー: 秋田書店
- 発売日: 2012/08/16
- メディア: コミック
- 購入: 2人 クリック: 13回
- この商品を含むブログ (15件) を見る
「それとも石黒正数は 超大物ではないかな?」(一部ウケ)

ま、彼は哲学的な作品というより落語的な味わいの「ねらった金庫」の漫画化を担当したんだがね。表紙で連想される名作「親しげな悪魔」は武蔦波氏の担当(ちょっとペテンっぽいよな、それ…)。
それはまた、別にして。
表題にはならないが、この巻の巻頭を飾るのが、「ひとつの装置」である。
この題を聞くとき・・・自分は12歳だか11歳だったか、とにかく中学に行く前、小学生の記憶に戻る。
甲本ヒロトの歌で
レコードプレイヤーが 「スイッチを入れれば必ずお前を十四歳にしてやる」と言ったんだ・・・という歌詞があるが、自分にとっては星新一SFがそれに当たるのかもしれない。
どういうふうに読んだかは、今でも覚えている。
何度かこのブログでも書いたポプラ社の、筒井康隆が情熱的に書いた少年向けSF入門書「SF教室」には、ブックガイドがついていた。
当時、地元の図書館は子どもルーム大人ルームが完全に分かれていた。
そのブックガイドにある名作、なまじ古典の名作なら子供用リライト版があったが、現役作家の星新一や小松左京、筒井康隆の紹介本は当然リライト版なんてない。
そこで「大人ルーム」にいくとSF全集(どこから出てたんだろう?)があり・・・星新一は通常出ている短編集をバラして再構成した「傑作100」というものだったはずだ。
それを図書館内で読んだとき・・・どれもが当然傑作だったが、この「ひとつの装置」に流れる哀しみ、風刺、詩情・・・すべてに度肝を抜かれたことを、昨日の様に思い出す。
世界的な名声を博している高名な科学者が、ある装置の開発に極秘に乗り出した。研究所の経費を流用し、さらに私財も投入して始まったこのプロジェクトは、のちに「完成まで、装置の内容は博士以外一切知らない」ままで、膨大な予算をつぎ込んだ国家の支援する公的事業となる。
これ以上の内容紹介は、ストーリーとテーマの根幹に触れるから差し控えたい。だがこの装置の意味、そしてここに「へそがある」ことは、この原作者が<人間の本質>に関して持っていたユーモラスな諦観と愛情を感じさせて実に秀逸だった。その装置をどうビジュアル化するかって大変なところだが、なんとなく自分が脳裏に浮かべていたイメージに似てもいるし、想像しなかった斬新な部分もあるのだよ。
(この作品はNHKのショート番組でも映像化されたが、わざと映像を抽象的に作った演出がなされ、個人的には評価も低いし、そもそも番外扱いすべきものだと思っている。)
その他の作品も
ランダムに感想
「ある意味、ソーシャル・ネットワークの予言かもしれん。しかしまあ、こんなロマンチック・コメディも書いてたんだよなこの人」「諸星大二郎の作品みたい」「いい話を、最後にぶちこわすか(笑)」「アフリカの武器商人を扱った某映画と、星野之宣『宗像教授』の第1巻を思い出した」・・・などなど。
それがどの感想かは、実際に読んでみてください。