<蒙古襲来>──海を渡ってやって来たのは本当にモンゴル人だったのか!?
一度目の文永の役(1274年)、ニ度目の弘安の役(1281年)で、日本に「蒙古」から大船団で襲来したとされる人々……
彼らを〝草原で遊牧をする民族"という、現代のわれわれがイメージする「モンゴル人」と同一と考えるのは間違いである。
史書『元史』『高麗史』には、当時の船員たちの名が記されている。そのほとんどは高麗人である。つまり元王朝=モンゴル人ではないのである。「元寇を『蒙古襲来』なのだから〝モンゴル人が来た"と思い込んでいるのと、今の中国、ロシア、朝鮮の実像を正確に把握できないのとは根が同じような気がしています」(著者)
では、元朝はなぜ高麗人をよこしたのか。
「元寇」をフビライ、ひいては世界史的な目線で、元と高麗を舞台として読み解くと、強国モンゴルに取り入り、「元」の日本遠征に自ら名乗りをあげた当時の高麗と現代の朝鮮半島の姿は、いろいろな面でオーバーラップしてくる。
一方、日本は二度の「元寇」から何を学んだのか。対外的に反省しすぎると世界では〝弱い"とみなされることを忘れていないだろうか。
本書では、蒙古、高麗、日本、それぞれにとっての「蒙古襲来」の意義と日本人の誤解を、当時の大陸をとりまく真実の歴史から検証する。
中央アジアの遊牧民を中心に、中国からロシアまで幅広く歴史研究をしてきた著者の真骨頂!<本書の構成><; br> 第一章 日本人のモンゴル観
第二章 モンゴルとは
第三章 高麗とは
第四章 蒙古襲来前夜
第五章 大陸から見た元寇
終章 その後
の中から。この本は話の本題よりは、根幹じゃないけど枝葉の話や体験談が面白かった。いくつかシェアしたい情報があったんだけど、まずこちら。
駐日モンゴル大使館の人たちがこぼしていました。会う日本人会う日本人が、必ずといっていいくらいに話題にするのが「義経=成吉思汗説」だと。モンゴル人のほうはしかたがないので、「義経=成吉思汗説」をいろいろ調べて、適当に話を合わせるらしいのですが、ほとほと困るというのです。モンゴルの英雄チンギス・ハーンが、史実でもなんでもないのに、源義経という日本人だと言われたのでは、モンゴル人はイヤな思いをするだけです。
第一章にも出した、マンガ『ハーン』が「義経=成吉思汗説」を採用しているのも、日本の中で、モンゴルの話をいかに日本人に引きつけて、身近に感じさせて興味を持たせるかという手段としては評価します。読者はそこに惹かれて買って読んでいるわけですから。
でも、当のモンゴル人相手に「義経=成吉思汗説」を話すのはやめたほうがいいと私は思っています。
日本人がモンゴル人相手に何も話題がなく、定番の三題噺さながらに出てくる話は「義経=成吉思汗説」、相撲、モンゴロイドなのだとか。
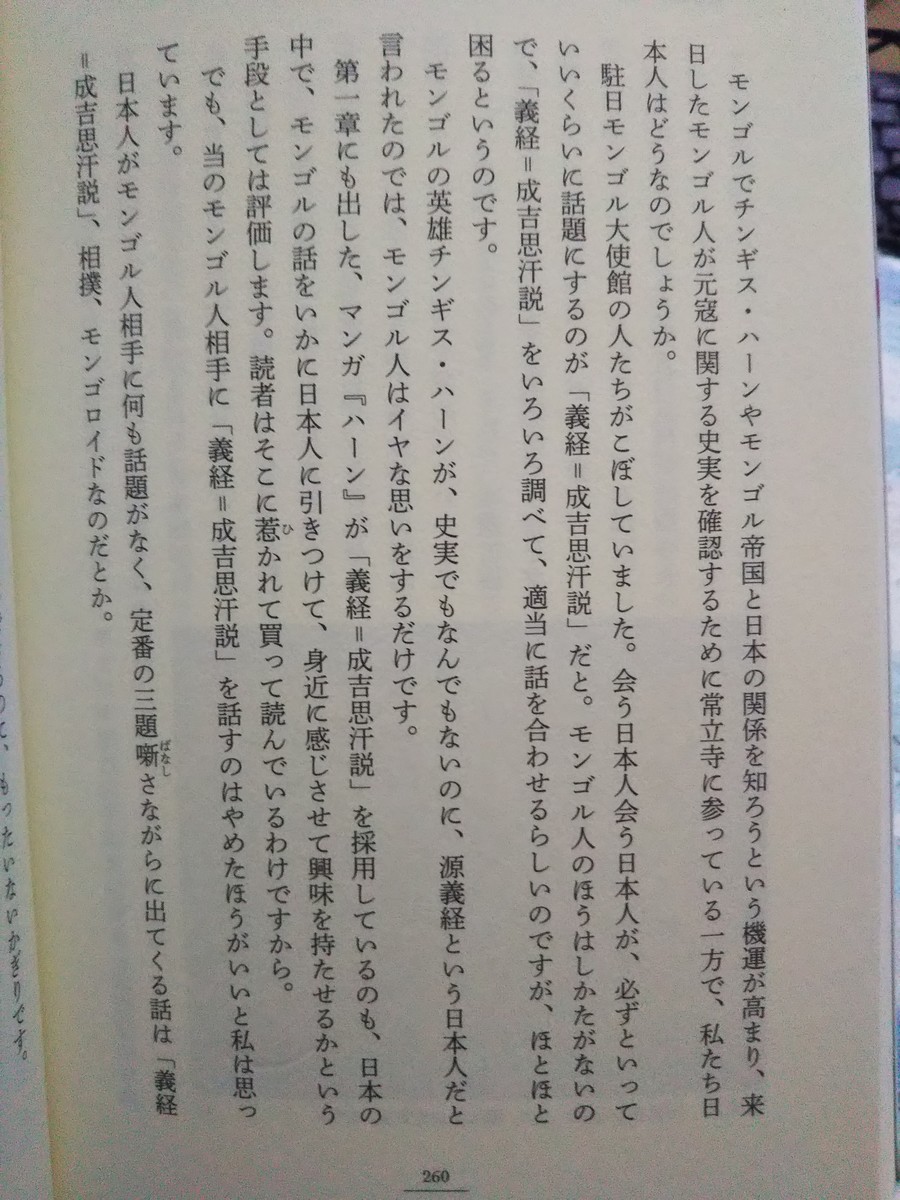
もうひとつ。
日本人のチンギスカン像に大きな影響を与え続けているのが、井上靖の古典「蒼き狼」だと思われる。
チンギスカン。
くり返される戦。惨忍冷徹な闘将は、何故にすべてを壊滅し尽くしたのか。上天より命(みこと)ありて生まれたる蒼き狼ありき。その妻なる惨白(なまじろ)き牝鹿(めじか)ありき。大いなる湖を渡りて来ぬ。オノン河の源なるブルカン嶽に営盤(いえい)して生まれたるバタチカンありき。――最初の祖先バタチカン生誕の伝承
風の如く蹂躙せよ。嵐の如く略奪せよ。
遊牧民の一部族の首長の子として生れた鉄木真=成吉思汗(テムジン=チンギスカン)は、他民族と激しい闘争をくり返しながら、やがて全蒙古を統一し、ヨーロッパにまで及ぶ遠征を企てる。六十五歳で没するまで、ひたすら敵を求め、侵略と掠奪を続けた彼のあくなき征服欲はどこから来るのか?
――アジアの生んだ一代の英雄が史上空前の大帝国を築き上げるまでの波瀾に満ちた生涯を描く雄編。用語、史実等の詳細な注釈を付す。著者の言葉
私が成吉思汗について一番書きたいと思ったことは、成吉思汗のあの底知れぬ程大きい征服欲が一体どこから来たかという秘密である。(略)
大国金を制圧しただけで収まらず、西夏、回鶻(ウイグル)と兵を進め、ついに回教国圏内にはいり、カスピ海沿岸から、ロシアにまで軍を派したのである。それも全く彼一人の意志から出ていることである。一人の人間が性格として持って生れて来た支配欲といったようなものでは片づきそうもない問題である。(「『蒼き狼』の周囲」)本書「解説」より
作者の心をこめて描いているのは、成吉思汗の生成の秘密である。彼をしてこういう運命に赴かしめた根本のものは何か。言わばモンゴル族の夢のみなもとを、彼の生のみなもとに結合させつつ、苦難にみちた生涯を辿らせているわけで、ここには外的事実だけでなく、成吉思汗の内心の苦悩をもつきとめようとする努力がある。(略)
狼の裔(すえ)として、自分こそ「狼になる」――これがモンゴルの男性の情熱の根源であった。
――亀井勝一郎(評論家)井上靖(1907-1991)
旭川市生れ。京都大学文学部哲学科卒業後、毎日新聞社に入社。戦後になって多くの小説を手掛け、1949(昭和24)年「闘牛」で芥川賞を受賞。1951年に退社して以降は、次々と名作を産み出す。「天平の甍」での芸術選奨(1957年)、「おろしや国酔夢譚」での日本文学大賞(1969年)、「孔子」での野間文芸賞(1989年)など受賞作多数。1976年文化勲章を受章した。
まず最初に余談を……これはかなり有名になってるトリビアな気がするが。
「蒼き狼」と言うが正確にはモンゴル語の言語ボルテ・チノの色を示すボルテは「斑点のある」とでも訳すべきものだった。漢語をへて日本語に訳されるとその意味が失われてしまったが、何しろ「蒼き狼」は言葉としてかっこいいので好みも広まってしまった。「白き牝鹿」能代も本当は黄色い毛を表すと言う。
本題。
ところで井上靖の小説「蒼き狼」は、モンゴル人ネイティブが読むと、そもそもチンギスハンの人物造形に大いに問題があるという。
……それは自分の出生にまつわる悩みです。
テムジンの父とされるイェスゲイはテムジンの産みの母であるホエルンを他の部族の男から略奪し結婚しました。ホエルンがテムジンを産んだのはその後です。テムジンは自分が本当に父イエスゲイの子供だろうかと悩みます。
テムジンの一人語りが続く場面で、弟達は間違いなくイェスゲイの息子だというのに自分一人だけは違うかもしれない、といった悩みが吐露されます。
テムジンのそうした悩みは日本の小説には馴染み深い題材です…源氏物語にも描かれているぐらいですから。しかしモンゴル人にとってそれは全くと言って良いほど理解できない心情です。モンゴル人曰く、モンゴルの男は出自に関して悩んだりはしない。誰の子供でも皆同じだと。
日本人が 作った映画を観たモンゴル人の中には、世界制覇をした男が、そのように自分の出自に関してウジウジと悩むような女々しい性格であるわけがない、と怒った人もいます。井上靖の描く「蒼き狼」のチンギスハンはモンゴル人とは思えないどころか、実はとても日本人的な人物なのです。
井上靖が作ったなんだかモンゴル人でなさそうな英雄像が一人歩きして、後世の作品でもそれが描かれイメージとして再生産されているのです。
…なんかすいませんね2。
いやでも、井上に成り代わって言い訳するが、言葉や服装や歴史はいろいろ調べがつくけど、別の時代の別の国、別の民族の「メンタリティ」をトレースするのって難しいもんでね・・・・・・。
ついついこの「〇〇に関してどうリアクションするか?」にお国柄が出ちゃう、舞台設定のその国っぽくなくなっちゃう、ってのはあるよね。
ハリウッドならぬニャリウッドとはいえ、そこで自分の理想の映画を撮りたいと思った監督さんが、プロデューサーさんに「土下座」して頼む、なんてこともあるのだし。
今現在でいえばヴィンランド・サガのトルフィンが、ちょっと価値観や心情が近代化チートしすぎて、そこに危うさを感じるところもある…だけどバイキングのメンタリティを再現するのはほぼ不可能だし、ホントに再現出来たら読者が共感できずにヴィンランドにいくまでに打ち切られただろうしで(笑)、あれはあれで借景的近代人であることに開き直り、そのまま突っ走ることで見えてくる風景があると思う。
おっと、まさに井上靖のそういうモンゴル小説、中国小説は「登場人物の心理などがあまりにも現代日本人風の”借景小説”だ」と批判を浴びたのだよな、大岡昇平らから。
ちょっと因果めぐりし話。
そもそも井上靖が書いた時代はまだ中国も情報が開放されておらず、資料も研究も不十分だった
イノウエ=サンが書いた小説も
「ドーモ、ジャムカ=サン!テムジン デス」
とか
「ホラズム殺すべし、慈悲はない」
ぐらいの解像度だったかもしれないではないか。……。誰だよ、そういうのがむしろ読みたい、とかいうやつは
もう幾つか、面白いトピックがあったのだけど、まずこのふたつの「どーもモンゴルさん、すいませんっした!!」な話題を紹介。



