「(ニュースは)言葉を固めて喋らなきゃいけない」「窮屈になってきた」はホンネかね…
3分ごろの発言をきこう。
「真意は違うかもしれないが」といえば、それはいくらでも違うだろうという推測はできるかもしれないが、しかし、もしこれが建前、表面的な嘘だとしてもなぜこういう建前を選んだのか、ってことになる。
その話は、そもそも退任表明をした際の記者会見のときに書きましたが…
「報ステ」降板の古館伊知郎氏”不自由”に挙げたのが「政権批判」でなく「ポリティカルコレクト」だったという… - http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20151227/p1
http://www.sankei.com/entertainments/news/151224/ent1512240014-n1.html
−−『不自由な12年間』という発言があった。どのあたりを不自由だと感じたのか「放送コードを守りつつも、いっぱいしゃべってきました。単純な話、物量的、時間的に制約がある。ニュースが終わって画面がスタジオに切り替わり、『この点でね、私はこう思うんです』と言った瞬間、『CMに行け』という指示が出ますから」
「それから、バラエティーやスポーツ実況の放送コードと報道の放送コードって違いますから。バラエティーなら、『ラーメン屋』と何の悪気もなく言えますが、報道は『ラーメン店』と、(『屋』ではなく『店』と)言わなければならないんですね。『おかしいでしょう』と、いつもスタッフとせめぎ合うんですけど」
「報道には報道特有のコードがありますし、人権を守らないといけないのは当たり前。また、テレビを見てくださる方にとって、バラエティーを見るモードと報道を見るスタンスは全然違います。そういう意味では、いろいろな不自由はありました」
ラーメン屋とラーメン店の違い、とかは知らんかったけど……
とにかく、「古舘氏の言うことを額面どおりに受け取るなら」、という前提をつけた上でいうと、時間の物理的制限とかは別にして、古舘氏が報道ステーションをやっているときに、もっとも「不自由」を感じていたのは、ポリティカル・コレクトネスによる制約だった…と、当人が言っているのだ!!!うーむ、うーむ、うーむ………。
四角四面の豆腐屋の娘
色は白いが水臭い。
古館氏の「がちっと固めた言葉を使わなきゃいけないのが窮屈」、「ラーメン屋でなくラーメン店と言わなきゃならない不自由」…記者会見と最後の挨拶でここまで直接的に言っているのだから、むしろ古舘降板を受けて語られる議題は「ポリコレ的な言葉の制約が、社会を委縮させる懸念」ということになるんじゃないだろうか(笑)

- 作者: 月刊『創』編集部
- 出版社/メーカー: 創出版
- 発売日: 1995/03
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログを見る
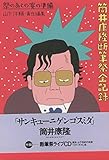
- 作者: 山下洋輔
- 出版社/メーカー: ビレッジセンター
- 発売日: 1994/09
- メディア: 単行本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (1件) を見る

- 作者: 星新一
- 出版社/メーカー: 新潮社
- 発売日: 1977/09/01
- メディア: 文庫
- 購入: 2人 クリック: 14回
- この商品を含むブログ (24件) を見る
山本七平「『空気』の研究」を大宣伝していただき感謝!!
報ステ・古舘キャスター3〈いい言葉を聞きました。空気を読むという人間には特性がある、読むから一方向に流れていってしまう、だからこそ反面で水を差すという言動が必要だ、その通りと感銘を受けました。つるんつるんの無難な言葉で固めた番組などちっとも面白くありません。人間がやってるんです〉
— 赤旗政治記者 (@akahataseiji) 2016年3月31日
【「空気を読む」という人間には特性がある。読むから一方向にどうしても空気を読んで流れていってしまう。だからこそ反面で「水を差す」という言動や行為が必要だと。
— 椴熊(Todoguma:壊憲断固阻止) (@todoguma) 2016年3月31日
私、 その通りだと思います。... https://t.co/fkCx0erBdt
番組中では、中島岳志氏から聞いた、と語っていたが、2月15日の番組では、中島氏はその元ネタも紹介していたらしい。
#報ステ
— 但馬問屋 (@wanpakutennshi) 2016年2月15日
中島氏
山本七平さんは一方で「水を差す」という言葉もあると書いている。水を差すのは空気が醸成された時にはとても重要だ、と。メディアは水の役割を果たすべきだと思う。視聴者に権力に忖度していると見られない姿勢を見せるべき。 pic.twitter.com/R0RP8znwnb
そう、中島氏はこの本を紹介したのだ。
目次をみると、『「空気」の研究』に続いて『「水=通常性」の研究』という章があるね。
あらゆる思想や論理を超えて日本人を支配する「空気」及びそれに呼応して勢力を振るう「水」の如き怪物「通常性」の正体をあばきつつ独自の論証を自在に展開する
- 作者: 山本七平
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 1983/10
- メディア: 文庫
- 購入: 84人 クリック: 673回
- この商品を含むブログ (200件) を見る
日本人を呪縛する「その場の空気」という怪物!「空気」とは何か?この超論理的存在の発生から支配にいたるメカニズムを根底から解明した「山本日本学」の決定版。 -
「空気」の研究(「空気」の研究
「水=通常性」の研究
日本的根本主義について)
「あたりまえ」の研究(指導者の条件
世論というものは
国境を出れば)
この機会にぽちりとどうぞ。
http://d.hatena.ne.jp/essa/20050406/p1
「空気」の研究Add Star
「とてもそんなことを言える『空気』ではない」という時の「空気」を論理的に考察した本である。
山本七平氏は、日本には「空気」という「まことに大きな絶対権を持った妖怪」がいて、これが日本における意思決定を左右し、非論理的で自滅的な方向へ組織を向かわせると言う。そして、その典型例として、太平洋戦争末期の戦艦大和の出撃に触れる。この文章を読んでみると、大和の出撃を無謀とする人びとにはすべて、それを無謀と断ずるに至る細かいデータ、すなわち明確な根拠がある。
だが一方、当然とする方の主張はそういったデータ乃至根拠は全くなく、その正当性の根拠は専ら「空気」なのである。従ってここでも、あらゆる議論は最後には「空気」で決められる。(P16)最後まで(「空気」を知らずに)反対していた伊藤長官という人は、
「陸軍の総反撃に呼応し、敵上陸地点に切りこみ、ノシあげて陸兵になるところまでお考えいただきたい」といわれれば、ベテランであるだけ余計に、この一言の意味するところがわかり、それがもう議論の対象にはならぬ空気の決定だとわかる。そこで彼は反論も不審の究明もやめ「それならば何をかいわんや。よく了解した」と答えた。この「了解」の意味は、もちろん、相手の説明が論理的に納得できたの意味ではない。それが不可能のことはサイパンで論証ずみのはずである。従って彼は、「空気の決定であることを、了解した」のであり、それならば、もう何を言っても無駄、従って、「それならば何をかいわんや」とならざるを得ない。(P18)
『「テレビのしんがり」を務めた』
ニュースステーションのことを「一番槍」と称したあと、自分を「テレビのしんがり」と表現した。
どういう意味かというと「テレビが独り勝ちだった時代があった。そこから時代が変わった。これから放送と通信が融合し、時代が乱世になっていく」という意味。
これは時代を象徴する言葉なのかもしれない。あとで文字起こししよう。
同時に、こんな不謹慎な想像もした(笑)
古館伊知郎氏「テレビのしんがり」かあ。
— gryphonjapan (@gryphonjapan) 2016年3月31日
名言だが、
じゃあ引き継いだアナウンサーは「敗残兵」かいな……
しかしまあ、名調子だ。あるいは喋りが「名人すぎた」ことがマイナスだったのでは…
冒頭だったか、「桜が咲いていますね」ということをしゃべっているのだけど、基本的に無内容、だけど「リズムとメロディ」で聞かせる(笑)
落語のしゃべりの要点を「要はリズムとメロディなんだ」と喝破したのは誰だったか。
古舘氏は、基本的にそれがよくもわるくも過剰だった。
リズムとメロディを強調してしゃべると、これまた良くも悪くも、内容の論理性とかとは別に、印象を一方に誘導することができる。古館氏の喋りは仮に右でも左でも、前でも後ろでも、上でも下でも…ちょっとそのリズムとメロディの過剰さが、ニュースとは調和しにくく、だから一種のうさん臭さがついてまわっていた。と、最終回でじっくり聞いてやっと気づいたのであります(笑)
これは例えば新聞記事をひとつ選んで、「これにポジティブな意味を持たせよう」「これにネガティブな意味を持たせよう」両方の意識で、その記事の文章を一字一句変えずに読んでみるとわかるかもしれない。
一字一句変えなくても、抑揚やアクセントである程度シロウトでもそれは可能だ。で、シロウトが目一杯やったつもりのリズムとメロディの過剰さは、古館氏にとっては通常運転だったのだな(笑)。だからこそ、プロレスの実況中継を丸ごと変える革命を成し遂げたのだ。
古舘氏の最後の挨拶って、要は「これからバラエティ、エンターテインメントをやります」という宣言だと推測できる。
この人も、それに期待し「勢力地図が塗り替わる」と予想している。
古館さんの報道ステーションが終了。『藝人春秋』にも一章を捧げたが、古館さんが報道からバラエティ界に帰還すれば、現在の勢力地図がオセロのように入れ替わるほどの絶対的才能の持ち主だけに今後の展開が楽しみだ。
— 水道橋博士 (@s_hakase) 2016年3月31日
